2025年10月まではS&P500企業はアナリスト予想を上回る決算を発表する企業が多数存在する中、主要株価指数は最高値を更新し続けてきました。
特に、MicrosoftやNVIDIAといった大型ハイテク株が市場を牽引し、AI関連のニュースや期待感が投資家心理を押し上げてきました。Microsoftの時価総額が初めて4兆ドルを超え、NVIDIAも5兆ドル突破への期待が高まるなど、市場は熱狂的な様相を呈しています。
しかし、このような上昇相場や、特定のセクター(現在のAI関連など)への過度な注目が集まる局面では、冷静な判断が不可欠になるのではないでしょうか。
市場は歴史的に繰り返されてきた人間の「恐怖と貪欲」の感情によって動かされるため、短期的な熱狂に惑わされないための普遍的な原則が求められます。
そこで本日は、1998年に伝説的投資家ボブ・ファレルが作成した、時代を超えて通用する「9つの投資ルール」】をご紹介させていただきます。これらのルールは、いかなる市場環境においても投資家が冷静さを保ち、長期的な成功を収めるための羅針盤となりますのでぜひ最後まで読んでみて下さいね。

ということで今回は「ボブ・ファレルが残した9つの不変投資ルール」についてです。
【この記事をみて分かること】
ボブ・ファレル 不変の投資9ルール
・ボブ・ファレルはどんな人
・ルール 1: 市場のトレンドは「平均への回帰」を繰り返す
・ルール 2: 一方向への過剰は、逆方向への過剰を引き起こす
・ルール 3: 「新たな局面」というものはなく、過剰な状態は決して永続しない
・ルール 4: 指数関数的なトレンドは長続きするが、調整は急激に進む
・ルール 5: 一般大衆は高値で買い、安値で売る
・ルール 6: 恐怖と貪欲は、長期的な決意よりも強い
・ルール 7: 市場は広い範囲に及ぶと最も強く、一握りの銘柄に絞られると最も弱くなる
・ルール 8: 弱気相場には三つの段階がある
・ルール 9: 全ての専門家の予測が一致した時、何か別のことが起こる
・不変の原則が激動の時代を乗り切る鍵(まとめ)
【差がつく投資ツール】
初心者でも使いやすいmoomoo証券アプリ
・バフェット銘柄を簡単にチェック可能
・ヒートマップで市場動向が一目で確認
・豊富な分析ツールを無料で使い放題!
- ボブ・ファレルはどんな人
- ルール 1: 市場のトレンドは「平均への回帰」を繰り返す
- ルール 2: 一方向への過剰は、逆方向への過剰を引き起こす
- ルール 3: 「新たな局面」というものはなく、過剰な状態は決して永続しない
- ルール 4: 指数関数的なトレンドは長続きするが、調整は急激に進む
- ルール 5: 一般大衆は高値で買い、安値で売る
- ルール 6: 恐怖と貪欲は、長期的な決意よりも強い
- ルール 7: 市場は広い範囲に及ぶと最も強く、一握りの銘柄に絞られると最も弱くなる
- ルール 8: 弱気相場には三つの段階がある
- ルール 9: 全ての専門家の予測が一致した時、何か別のことが起こる
- 不変の原則が激動の時代を乗り切る鍵(まとめ)
ボブ・ファレルはどんな人
ボブ・ファレル(Bob Farrell)氏は、米国の金融業界で伝説的な存在として知られるベテランの投資ストラテジストです。特に、大手証券会社であるメリルリンチ(Merrill Lynch)で長年にわたりチーフ市場アナリストとして活躍し、ウォール街で45年以上のキャリアを築きました。
彼の最大の功績は、市場の動きや投資家の心理を読み解く洞察力に優れていた点で、彼は単なるテクニカル分析(チャートの分析)だけでなく、市場のムードや投資家心理が相場に与える影響を重視していました。
例えば、「極端な状況(行き過ぎた過熱や悲観)は続かない」「相場は平均値に戻る」といった、市場の循環や過熱感を戒めるルールが含まれています。これらのルールは、市場の心理学を理解し、冷静な判断を保つための指針として重要視されています。
彼の哲学は「市場は歴史を繰り返す」という視点に基づいており、投資初心者が市場の変動に惑わされず、長期的な視点を持つための貴重な知恵を提供してくれています。
今回はボブ・ファレルが提唱している普遍的な9つの投資ルールについてを個人投資家目線でポイントを絞ってまとめましたのでご自身の投資スタンスを決めていくうえでの参考に一読下さい。
ルール 1: 市場のトレンドは「平均への回帰」を繰り返す

市場のトレンドは時間の経過とともに平均に回帰する傾向があるというもの。
これはある方向に行きすぎたトレンドは、その長期的な平均値に必ず戻ることを意味しています。
市場が非常に強い上昇トレンドや、逆に強い下降トレンドの最中にあるときでも、価格が長期移動平均に回帰する現象は頻繁に発生します。この原則は、熱狂的な相場の中で過度に高騰した資産が、最終的にはその妥当な水準へと引き戻される可能性を常に示唆しています。
ルール 2: 一方向への過剰は、逆方向への過剰を引き起こす

相場は、まるで振り子のような動きを示すことがあります。一方向に過剰に動いた後、今度はその逆方向に過剰に動くという揺れを繰り返すと考えているようです。この現象の最も顕著な例の一つが、1999年のドットコムバブルでした。
当時、ナスダック総合指数は52週移動平均線から40%以上も上昇するという「ものすごく過剰な状態」にありました。
しかし、この過剰な上昇は、2000年から2001年にかけての急落を引き起こし、今度はナスダックが「過剰に売られすぎ」の状態に陥ることになりました。過度な期待や投機熱が集中した分野は、その反動で極端な調整を迎えるリスクを常に内包している点は理解しておく必要があるのではないでしょうか。
ルール 3: 「新たな局面」というものはなく、過剰な状態は決して永続しない

投資家が最も危険な感情に陥るのは、「今回は違う(This time is different)」と信じるときですが、ファレルは、「新たな局面(New Era)」というものは存在せず、過剰な状態は決して永続しないと断言しています。
過去100年の間、市場では様々な銘柄群が投機的なバブルに見舞われていて、1920年代には自動車、ラジオ、電気が相場を支え、1970年代前半にはニフティ・フィフティと呼ばれる優良株50銘柄が強気相場を演出。さらにバイオテクノロジーのバブルは10年に一度くらいの頻度で登場し、そして1990年代後半にはドットコムバブルがありました。
ファレルは、「今回だけは違う」という言葉は、おそらく投資において最も危険な言葉であるとしています。
世紀の相場師ジェシー・リバモアもまた、この不変の原則を強調しています。彼が残した教訓は、「ウォール街に新しいものはなく、今日株式市場で何が起ころうと、それは以前に起こったことであり、またこれからも起こるだろう」というものです。
数年ごとにホットな銘柄群が登場し、投機ブームは起こりますが、永遠に続くものはないと知っておけるといいのではないでしょうか。
ルール 4: 指数関数的なトレンドは長続きするが、調整は急激に進む

市場が指数関数的に上昇または下降するトレンドは、投資家が思っているよりも長く続くことがしばしばあります。ホットなグループが最終的に平均値に戻るとしても、強いトレンドはしばらく持続する可能性があります。
しかし、注意すべきは、このトレンドが横ばいで緩やかに調整されることはほとんどないという点です。トレンドが終了する時、その修正は急激に進む傾向にあるというのがファレルの考え方です。
例として、上海総合指数は2005年7月から2007年10月まで上昇を続けました。この期間中、指数は2006年7月、2007年初頭、2007年半ばにわたり「買われすぎの水準」だと何度も指摘されていましたが、トレンドは伸び続け、これらの水準は天井にはなりませんでした。
しかし、トレンドが反転した場合、その調整は迅速に訪れることが多いと理解をしておけるといいのではないでしょうか。
「AIで市場の先読み」
ほったらかし投資術をはじめませんか!
・運用を自動化して、手間なしの資産運用
・40以上の先行指標分析で、市場動向予測
・月1回程度の頻度で投資配分が自動で調整
ルール 5: 一般大衆は高値で買い、安値で売る

このルールは、市場のセンチメントを理解する上で非常に重要です。
平均的な個人投資家は、市場の天井で最も強気になり、市場の底で最も弱気になります。この結果、彼らは市場が高騰した「高値で多く買い」、市場が暴落した「安値で少なく買う」という、長期的なリターンを損なう行動パターンに陥りがちだと。
したがって、ファレルは、過度に強気なセンチメントは市場の天井を警告し、過度に弱気なセンチメントは市場の底を警告するサインとして捉えるべきだと主張しています。
この点について、投資の神様バフェットも同様な発言をしていて「人々が慎重な時は貪欲に、人々が貪欲な時は慎重になれ」という名言を残しています。
現在、消費者の間ではインフレへの懸念が続く一方、雇用データの弱さを背景に失業を心配する声が増え、消費の伸びを支えているのは主に富裕層であるといった経済状況の悪化を示すデータも出てきています。
このような状況下でセンチメントが極端に振れた場合、それは市場の転換点のヒントとなる可能性があるのではないでしょうか。
ルール 6: 恐怖と貪欲は、長期的な決意よりも強い

投資における最大の敵は、市場の変動そのものではなく、投資家自身の「感情」です。ファレルは、恐怖と貪欲は長期的な決意よりも強い力を持つと指摘します。
• 恐怖: 急激な下落や大きな損失は恐怖心を煽り、戦いのさなかでパニック的な判断(狼狽売りなど)を下すことになりかねません。
• 貪欲: 同様に、急激な上昇や大きな利益は過信を招き、長期的な計画(リスク管理や分散投資など)からの逸脱を招くことが多くあります。
このようにファレルは感情をコントロールし、市場の喧騒から一歩引いた視点を持つことが、優れた投資家になるための鍵だと説明してくれています。
これをイギリスの小説家ラドヤード・キップリングの言葉を借りるなら、「周りが頭を抱えて(パニックになっている)時でも、自分は冷静でいること」が大切だということになります。
これができれば、より優れたトレーダーや投資家になれます。感情が高ぶった時には、一息ついて一歩下がり、より遠くから状況を分析することが極めて重要だと理解ができるのではないでしょうか。
ルール 7: 市場は広い範囲に及ぶと最も強く、一握りの銘柄に絞られると最も弱くなる

ファレルは市場の「幅広さ(ブレッド)」を見ることは、ラリーの信頼性を判断する上で重要で、市場が広い範囲の銘柄に及ぶとき、それは最も強い状態を示すと教えてくれています。
反対に、一握りの有料銘柄に絞られて上昇しているとき、市場は最も弱くなります。狭い幅でのラリー(少数の銘柄だけが牽引する上昇)は、市場参加者が限られていることを示しているので失敗する確率が平均以上になります。
現在の市場でも、指数がしっかり上昇しているものの大型ハイテク株だけが上昇して、それ以外の多くの銘柄が下落しているといった状況が見られますよね。

実際に記事作成をしている2025年11月時点でS&P500のADライン(騰落株線)を見ておこうと思います。ちなみにADラインはある一定期間内に上昇した銘柄数から下落した銘柄数を差し引いた値を表します。
つまりS&P500構成銘柄の動向として全体もしくは一部が売れているなどが分かるのがADラインです。実際に11月時点では若干ですが下落していて一部の大型銘柄が引っ張っている様相になっていることが分かりますよね。
市場が上昇し続けるためには、少数の大型株が先導するだけでは不十分であり、ラリーの信頼性を高めるには、中小型株も参加する必要があると分かります。全ての上昇を支える「全ての船を持ち上げるようなラリー」こそが広範囲にわたる強さを示し、さらなる上昇の可能性を高めると理解ができるのではないでしょうか。
ルール 8: 弱気相場には三つの段階がある

弱気相場(ベアマーケット)は、単なる下落ではなくて、ファレルは弱気相場には「急落」「反射的な反発」「長引くファンダメンタルズの悪化」という3つの段階があると説明しています。
1. 急落
相場は多くの場合、まず急激な下落で始まる。
2. 反射的な反発
この急落の後、市場は一時的に売られすぎの反動で一部が戻される「反射的な反発」を見せます。
3. 長引くファンダメンタルズの悪化
その後、下落は続きますが、そのペースはより緩やかになり、経済のファンダメンタルズ(基礎的条件)の悪化に伴ってさらに悪化していく段階へと移行します。
ダウ理論においても、弱気相場は3回の下落を経験し、その間に反射的な反発があるとされています。
ルール 9: 全ての専門家の予測が一致した時、何か別のことが起こる

最後のルールは、ファレルの逆張り思考を最もよく表しています。
全ての専門家の予測が一致し、ある一つの方向に賭け始めた時、その予測とは「何か別のこと」が起こる可能性が高まると言っています。
具体的には、全てのアナリストがある銘柄を「買い」と評価し、市場参加者の意見が一方向に傾いた時、その銘柄にとって残された道はただ一つ、ダウングレード(格下げ、つまり評価の引き下げ)でしかありません。
ライターやアナリストの過度に強気なセンチメントは、市場の天井や過熱感を警告するサインとして見るべきとのこと。
不変の原則が激動の時代を乗り切る鍵(まとめ)
今回はボブ・ファレルの9つの投資ルールについてまとめてみました。
1998年に作成されてから四半世紀以上が経過した現在でも、その普遍性を保ち続けています。現在、市場はMicrosoftやNVIDIA、OpenAIといったAI関連企業が牽引する新たな技術革新の波に沸いていますが、過去のドットコムバブルやニフティ・フィフティの時代と同じく、市場の過熱感や人間の感情のサイクルは繰り返されています。
投資家として成功を収めるためには、最新のニュースや技術動向を追うことと同様に、市場が持つ平均回帰の傾向、過剰が永続しないという歴史的な教訓、そして何よりも恐怖と貪欲という自身の感情とどう向き合うかを理解することが不可欠です。
激しい相場変動の中、「周りが頭を抱えている時でも自分は冷静でいること」、そしてファレルの9つのルールを常に心に留めておくことが、長期的な投資の決意を支え、市場で生き残るための鍵となるのではないしょうか。
ぜひ投資スタンスを決めていく、一助になれば幸いです。
最後まで読んでいただきましてありがとうございました!
【情報収集に必須で使えるツール!】
投資初心者でも安心なmoomoo証券

口座開設がまだの方はこの機会にぜひ!



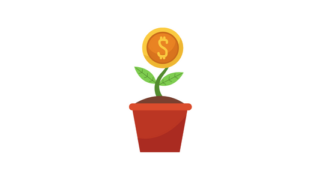


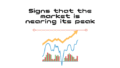
※当ブログではアフェリエイトによる広告を掲載しています※